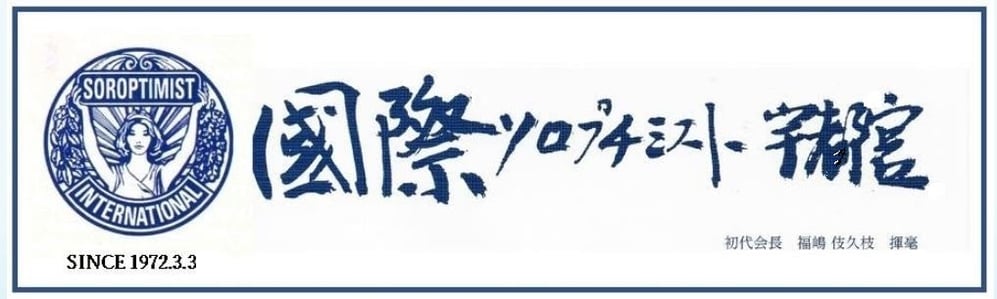元気な人生100年のために~何をどう食べる?
もちづき女性クリニック
理事長 望月善子
私たちは今、「人生100年時代」と呼ばれる長寿社会を生きています。しかし、ただ長く生きるだけではなく、「元気で充実した生活」を送ることが大切です。その鍵を握るのが毎日の食生活であり、大規模な疫学研究でも、健康長寿と食事・栄養の関係が大きいことが明らかになっています。
ライフステージごとに健康課題は異なりますが、緑茶、きのこ、ミカン、魚などを多く摂取している人々では、死亡リスクや要介護・認知症の発症リスクが低いことが確認されています。また、ごはんを中心とした日本食の食パターンは、循環器疾患による死亡リスクや要介護・認知症の発症リスクを減らし、健康寿命の延伸に寄与することがわかってきました。
しかし高齢になると食が細くなり、たんぱく質やカルシウム、ビタミンDなどの摂取が不足しやすく、フレイル(虚弱)やサルコペニア(筋肉量減少)の原因となります。低栄養は転倒や寝たきりのリスクを高めるため、個々の身体活動レベルや疾患・栄養状態に応じて調整は必要ですが、体重1kgあたり30kcal程度のエネルギーと、少なくとも体重1kgあたり1.0gのたんぱく質摂取が不可欠です。さらに、ビタミン(D、A、B群)を十分に摂り、多様な食品から栄養素を補うことも望ましいとされています。たんぱく質を効率よく活用するためには、主食の炭水化物もしっかり摂取し、エネルギー不足を防ぐことも重要です。
そして、「何を食べるか」だけでなく「どう食べるか」も大切です。ゆっくりよく噛んで食べることは消化吸収を助けるだけでなく、脳の活性化や認知症予防にもつながります。孤食を避け、家族や友人と一緒に食卓を囲むことで、より食事の楽しさを感じることができるでしょう。食べることに関しては、自分自身が主治医です。「食べる口」と「しゃべる口」の健康を守り、日々の小さな積み重ねが元気で豊かな人生100年を支える大きな力となります。